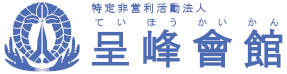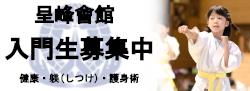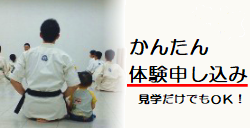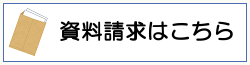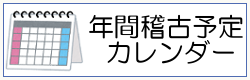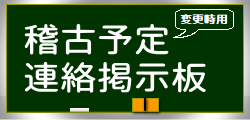組討道とは
ここに書かれている内容は「組討」が様々な捉え方をされている現代において、総ての人が正確に知る事が大切と考え、数多くの歴史書や一次資料から、近藤修匡が、ここにまとめました。
「組討道」とは
「組討道」とは、近藤修匡を開祖とする護身術です。
相手と戦う為の実技指導を護身術とされているところがありますが、「組討道」では、危機から安全に離脱する為の時間を作る事を目的とする、現在までに例の無い護身術です。
実技は、逃げる事ができない場合に使用するもので、常に「先の先」を取り、突きと蹴りを基本とし、携帯できる得物(武器)も使用しながら相手を投げ、「制圧」又は「確保」するという、当事者同士が終息を受け入れられる「武道」です。
「組討道」という自分の身を守るという護身術と、「組討」という相手を討ち取る(殺す)事を目的とした闘法は、そもそも求める結果に違いがあり、「組討道」は、古流武術ではなく、近代武道に属します。
また、受身技法という相手からの攻撃を待ってから対応するという技法では、死んでしまうかもしれません。また、膨大な量の「形」を習得する稽古では、それら総てを習得する前に命が尽きてしまうかもしれません。これらの技法は相手に必ず勝てる装備や立場を必要とします。
問い合せ先
呈峰會館事務局 電話番号 0564-54-3060
お問い合わせ時間 月曜日~日曜日 10:00~22:00
*お休みはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。