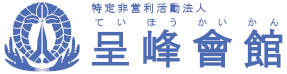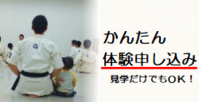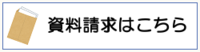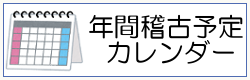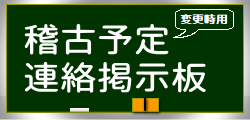入会案内
始める前に(他に無い当會館の特徴)
始める前に(他に無い当會館の特徴)
- 親子で一緒に、同じ時間に稽古ができます。もちろん親子でなくても大丈夫です。
- 腕立て伏せや腹筋など一人で出来る事は、稽古中行いません。稽古をしに来きているからです。
- 一般部登録の方は、他の支部で、週に何度稽古をしても余分な費用は頂きません。
*他の支部で稽古をする際は、會館より毎年発行の会員証又は、警察官は警察手帳の提示が必要となります。もし無い場合は稽古をご遠慮させて頂く場合が有ります。 - 30歳を過ぎて競技に参加できなくなると道場の片隅に追いやられるというのがごくごく一般的なこの世界ですが、当會館では3歳以上なら上限・性別は問いません。皆一緒に稽古します。
- 怪我はしてはいけないものと考えます。稽古中の怪我を自慢するのはだめです。怪我をして稽古ができない時間を作るより、その分、正確な稽古を沢山経験したほうが、技量も上がり健康にもなれます。
- 競技(試合)を意識した指導はいたしません。
- 体力に不安のある方は、個々の技について20回行う所を減数して結構です。ゆっくり回数を増やすようチャレンジしましょう。
- 学校や仕事の都合で遅れてもかまいません。その場合は十分準備体操をし、稽古に参加してください。
- 同居の家族で3人目からは、月会費が半額となります。月会費以外の費用請求及び競技・グッズの強制は一切ありません。
- 入門制限があります。規約にて決まっておりますが、体験時と入門時に説明又は書面にてお渡しします。
- 初期費用は、分割払いでも大丈夫です。
稽古内容
準備体操・基本稽古・相手をコントロールする稽古・指定組手・ 自由組手・投技・制圧方法とステップアップしますが、それぞれの技についてのポイントを毎回指導者が説明しますので、合理的に理解と上達できます。
通常の稽古は基本稽古が主となります。技を覚えて、その有効性を理解しないと、組手をやってもその人固有の身体能力に頼るだけとなるからです。
稽古に参加の際には
- 稽古に来たら、必ず道場と神前(神棚のある場合のみで結構です。)に挨拶しましょう。
- 稽古中の返事はすべて「はい」ではなく、「押忍」と言いましょう。
- 稽古の最初と最後に「黙想」をし、皆で「道訓」を唱和します。
- 最初は少し違和感がありますが、すぐになれると思います。
- まずは稽古前の掃除から始めましょう。
オリジナルカリキュラム
呈峰會館では、当會館独自のカリキュラムがあります。
(會館独自の実践的な稽古体系と日本古来の精神性を融合したもの)
当會館の全支部ではカリキュラムに沿って同じ指導をしておりますので、効率的に技量が上がります。(強くなります)
*怪我をして稽古を休むより、カリキュラムに沿った稽古を沢山して頂く方が、効率的に強くなり、そしてその運動量に比例して健康になります。
カリキュラムについて…従来の空手の稽古との比較…
~従来の空手の稽古では~(多くの空手流派の指導形態)
- 普段の稽古以外、又は稽古中に重い物を持ったりする補強運動(いわゆる筋トレ)が必要となります。
- 稽古の中で、退会者を少なくする為にゲーム性を取り入れた稽古を行います。(飽きてしまって辞める事が一番多い様です)
- 審査において、普段行わない技や審査用の科目を覚えないといけない側面があります。
- 試合(競技)が非常に重要という考えから、基本より試合に有効な技を反復練習します。
- 試合用の稽古は、組手が主体となりますので、怪我が増えます。
- 子供・大人・女性・壮年、それぞれの稽古が別々のものとなります。試合に参加出来なくなれば、形(かた)中心の稽古を行います。
~当會館の稽古では~(当會館固有の指導形態)
- 補強運動は必要ではありません。普段の稽古の中に相当の運動が網羅されています。自分の体以外の重い物を持つ必要はありません。
- 稽古は組討道(空手道)という武道を目的に通って来て頂く訳ですから、遊びを取り入れる必要は無いと考えます。むしろ稽古時間が足りなくなってしまいます。
- 実際に使える事のない形式上の技・科目は、覚える必要はありません。
- 試合(競技)は必要ありません。ですので試合の案内をする事もありません。ただ、試合に参加してみたい人を止める訳ではないので、本部事務局までお問合せ下さい。
- 準備体操・基本稽古・相手をコントロールする稽古が主体となりますので、怪我はまずありません。
- 3歳以上の総ての人が同じ基本を一緒に稽古します。他の空手教室に無い当會館固有の指導形態です。形は伝統空手の稽古方法なので、行う予定はありません。
まとめ
- 折角この武道を始めて頂く訳ですから、格好良く見せる事よりも、実際に使えるようになって頂き、本当の自信に繋がるものを覚えて頂きたいと思います。
- 呈峰會館で指導している「護身術」の実技稽古により、「基礎体力」の向上と「心身の健康」が身に付き、会社や学校とは違った環境での居場所が見つかります。
お問い合せ先
三河本部・事務局(郵便物の送付はこちらへお願い致します。)
住 所 :〒444-0203 愛知県岡崎市井内町字西浦48番地2
電話番号:0564-54-3060 FAX:0564-54-3054
e-mail :info@teihou.org
※上記emailにメール発信時は、全角@を半角@に修正しご利用ください。
総本部
住 所 :〒466-0051 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目12-4
電話番号:052-883-0333
お問い合わせ時間 月曜日~日曜日 10:00~22:00
*お休みはありません。お気軽にお問い合わせ下さい。